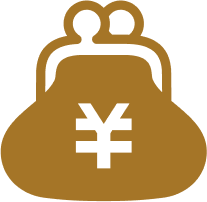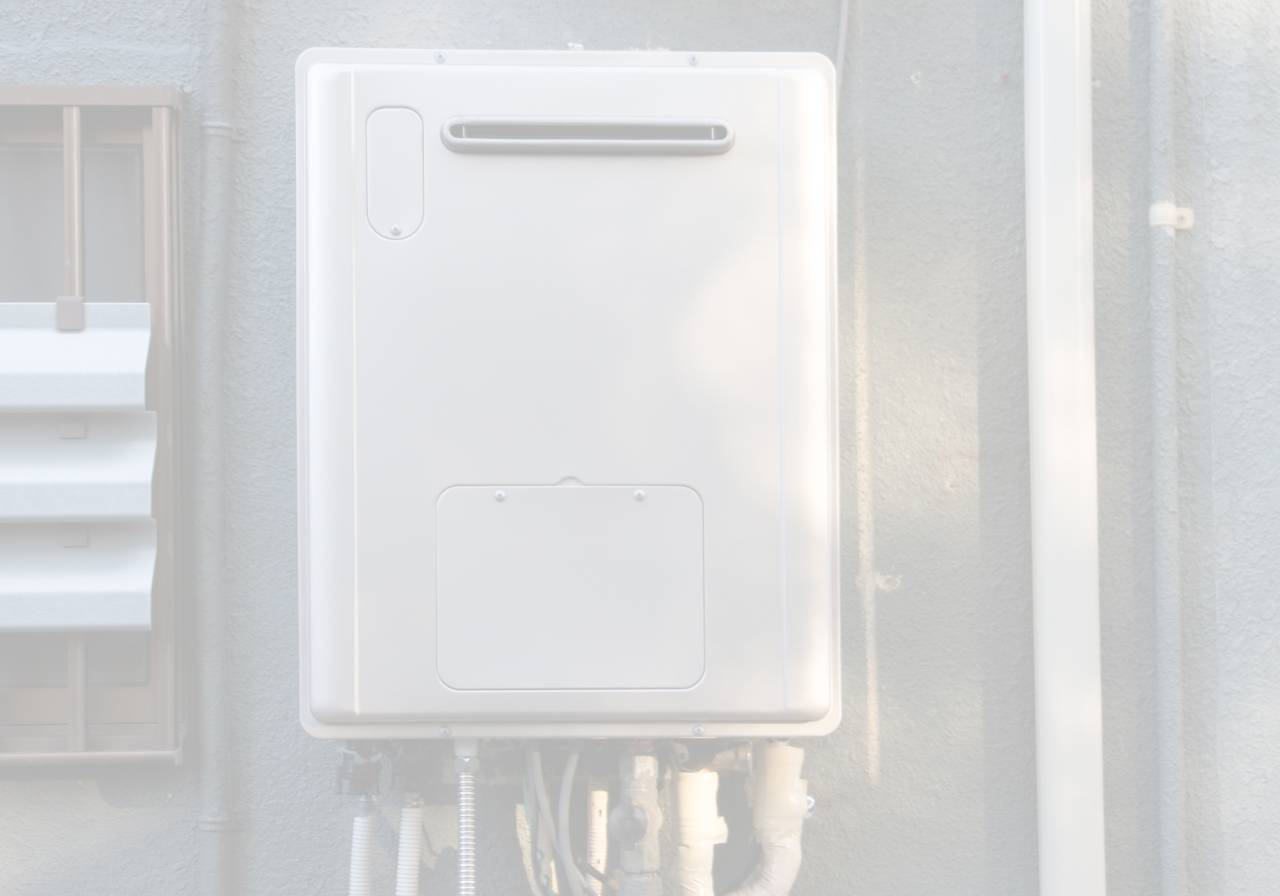
給湯器の水抜き方法をわかりやすく解説!凍結防止策や凍結したときの対処法をご紹介
寒冷地や冬季の厳しい寒さは、給湯器にとって大敵。凍結による故障を防ぐため、適切な水抜きが不可欠です。この記事では、給湯器の水抜き方法や凍結防止策、万が一凍結してしまった場合の対処法を詳しく解説します。
本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...
給湯器の凍結リスクとその影響について
冬の厳しい寒さが続くと、給湯器に凍結のリスクが高まります。特に屋外に設置されている給湯器は、気温が0度以下になると配管内の水が凍り、給湯器の正常な動作を妨げる可能性があります。凍結対策を怠ると、深刻なトラブルを招き、修理や交換が必要になることも。ここでは、給湯器が凍結した際に考えられるトラブルや故障リスクについて詳しく解説します。
凍結が引き起こすトラブル
給湯器の凍結は、主に配管や給水・給湯口に溜まった水が原因です。水が凍ると、体積が膨張し、配管内部に圧力がかかります。この圧力が加わることで、以下のようなトラブルが発生します。
- お湯が出ない: 凍結によって配管が詰まり、お湯の供給が止まることがあります。特に、寒冷地では朝起きた時にお湯が使えないというケースが多く見られます。
- 水漏れの発生: 凍結した水が解凍される際、配管にひび割れが生じ、水漏れが発生することがあります。これが原因で住宅内や周辺に水漏れ被害が広がることもあります。
- ガス給湯器の誤作動: 凍結が原因でガス供給や点火に問題が生じ、給湯器が正常に作動しなくなることもあります。安全装置が働き、運転停止になる場合も少なくありません。
凍結による給湯器の故障リスク
給湯器の凍結がもたらすリスクは、トラブルだけにとどまりません。凍結が進行すると、給湯器そのものにダメージを与え、故障へと繋がる可能性が高まります。特に注意すべき点は次の通りです。
- 配管の破損: 凍結による膨張圧で配管が破裂することがあります。これにより、配管交換が必要になり、修理費用がかさむ原因となります。
- 熱交換器の破損: 給湯器の内部にある熱交換器も凍結の影響を受けやすいパーツです。凍結した水が膨張すると、熱交換器が破損し、修理が不可能な場合は給湯器全体の交換が必要になることもあります。
- センサーやバルブの故障: 凍結により、給湯器内部のセンサーやバルブが正常に作動しなくなることがあります。これにより、誤作動が頻発し、最終的に給湯器全体が使えなくなるリスクがあります。
凍結によるトラブルは予防が最善策です。日常的なメンテナンスや事前対策を行うことで、給湯器の凍結リスクを大幅に減らすことができ、冬でも快適な暮らしを維持することができます。
給湯器の水抜き方法【基本編】
給湯器の水抜きは、寒冷地や冬場において給湯器を保護するために重要な作業です。水が凍結すると、給湯器や配管にダメージを与えるリスクがあるため、凍結防止策のひとつとして水抜きを定期的に行う必要があります。ここでは、水抜きが必要な理由や手順について詳しく解説します。
水抜きが必要な理由
給湯器内に残った水は、気温が0度を下回ると凍結する可能性があります。凍った水は膨張し、配管や給湯器の内部に過度な圧力をかけるため、これが原因で配管が破裂したり、給湯器が故障したりすることがあります。特に長期間家を空ける場合や、夜間の冷え込みが厳しい時期には、使用しない間の凍結防止策として水抜きを行うことが不可欠です。
水抜きは、凍結による修理や交換のリスクを未然に防ぐための基本的な対策のひとつです。特に寒冷地では、凍結が引き起こすトラブルが頻発するため、これを避けるための事前の準備として重要視されています。
水抜きの準備
給湯器の水抜きを行う際には、以下の道具と準備が必要です。
- モンキーレンチ: 給水・給湯のバルブを開閉するために必要です。
- バケツや容器: 抜き出した水を受け取るために使用します。
- タオルや雑巾: 水がこぼれた際の掃除用に用意しておくと便利です。
また、事前に給湯器の取扱説明書を確認しておき、機種ごとの水抜き方法を把握しておくことも重要です。特に、機種によっては特殊な手順が必要になる場合があるため、準備段階で確認しておくことがトラブルを防ぐポイントです。
給湯器の水抜き手順
水抜きは以下の手順で行います。正しく行うことで、凍結リスクを効果的に軽減できます。
電源をオフにする
まず、給湯器の電源を完全にオフにします。これは安全を確保するための基本的なステップです。
給水バルブと給湯バルブを閉める
給水・給湯のバルブを閉じ、これ以上水が供給されないようにします。
排水栓を開ける
排水栓を開けて、給湯器内部の水を排出します。排水栓の位置は機種によって異なるので、説明書を参照してください。
配管内の残り水を確認する
給水・給湯配管にも水が残っていることがあるため、必要に応じてバルブを開け、配管内の水も完全に抜きます。バケツを使って、排出される水を受け取ると良いでしょう。
水抜き完了後の確認
全ての水が抜けたことを確認したら、排水栓を元に戻し、バルブも閉じます。ここでタオルや雑巾で周辺をきれいに拭き取っておくと、次回の使用時にスムーズです。
この手順をしっかりと守ることで、給湯器の凍結リスクを大幅に軽減でき、寒冷時にも安心して使える状態を保つことができます。
給湯器の凍結防止策
冬の寒冷な時期に給湯器の凍結を防ぐためには、事前の対策が不可欠です。特に寒冷地や夜間の冷え込みが厳しい環境では、給湯器の凍結を防ぐための基本的な対策を施すことで、故障やトラブルを未然に防ぐことができます。ここでは、給湯器の凍結を防ぐために有効な3つの方法をご紹介します。
自動凍結防止機能の活用
多くの最新型の給湯器には、自動凍結防止機能が搭載されています。この機能は、気温が急激に下がり凍結のリスクが高まると、自動で給湯器内部の配管にわずかに水を流したり、内部ヒーターを作動させることで凍結を防ぐ仕組みです。自動凍結防止機能を活用するためには、給湯器が常に通電している状態でなければなりません。そのため、給湯器を使用しない場合でも電源は入れておくようにしましょう。
また、この機能が正常に作動しているかどうか定期的に確認することも重要です。取扱説明書に記載されている手順をもとに、自動凍結防止機能のチェックを行いましょう。特に、長期間使っていない場合や寒冷地に設置している給湯器では、動作確認をしておくことで安心して冬を迎えることができます。
保温対策の実践方法
凍結を防ぐもう一つの効果的な方法が、給湯器や配管に保温対策を施すことです。給湯器本体や配管に保温材を巻きつけることで、外気温の影響を受けにくくし、凍結のリスクを軽減できます。特に、屋外に露出している配管は凍結しやすいため、断熱材や保温チューブをしっかりと巻いておくことが重要です。
さらに、給湯器専用のカバーを設置することも有効です。カバーは給湯器を直接寒風や雪から守り、内部の温度を安定させる効果があります。また、保温材やカバーを使用する際は、給湯器の空気取り入れ口や排気口を塞がないように注意しましょう。これらの開口部がふさがると、給湯器の運転に支障をきたすことがあります。
夜間の予防策
寒冷地や気温が特に下がる夜間には、さらに凍結防止の対策を強化することが求められます。特に夜間は、気温が最低になる時間帯であり、凍結リスクが最も高まります。ここで簡単にできる予防策のひとつが、給湯器にわずかな水を流し続けることです。配管内で水が常に流れていれば、水が凍ることを防ぐことができます。水を少量でも流し続けることで、凍結防止効果が期待できるため、夜間や外出時に設定しておくと安心です。
また、給湯器の温度設定を高めにしておくことも有効です。低温のまま設定していると、水が凍りやすくなるため、使用する際の温度を高めに設定しておくことで、凍結リスクを減らせます。これらの対策は、特に夜間に気温が急激に低下する時期に有効です。
これらの凍結防止策をしっかりと実践することで、冬場の給湯器の凍結リスクを大幅に減らすことができ、トラブルなく快適に給湯器を使用することができます。
給湯器が凍結してしまった場合の対処法
冬場の寒波や急な冷え込みで、給湯器が凍結してしまうことがあります。凍結によって給湯器が正常に機能しなくなると、日常生活に大きな支障をきたします。そんな時に慌てないために、凍結時に確認すべきことや、応急処置の方法、そして専門業者に依頼するタイミングについて、詳しく解説します。
凍結時にまず確認すべきこと
給湯器が凍結してしまった場合、まずは慌てずに以下の点を確認しましょう。
給湯器の電源が入っているか
凍結時、給湯器の電源がオフになっていると、自動凍結防止機能が働かず、凍結がさらに進行してしまうことがあります。まずは給湯器の電源がオンになっているかを確認してください。
給湯器の状態をチェック
給湯器の表示パネルにエラーメッセージが表示されている場合、その内容を確認しましょう。多くの給湯器は凍結時にエラーコードを出し、運転を停止する機能が搭載されています。エラーメッセージは、凍結や他の故障が原因かを判断する手がかりとなります。
水が出ないか確認する
給湯器自体ではなく、配管部分が凍結している可能性もあります。蛇口をひねって水が出るかどうかを確認し、給湯器のどこが凍結しているかを把握しましょう。
応急処置の方法
給湯器や配管が凍結していることが確認できたら、自分でできる応急処置を試してみましょう。ただし、無理に修理しようとすると給湯器を傷める可能性があるため、慎重に対応することが大切です。
給湯器の電源をオフにする
凍結したまま給湯器を使用しようとすると、機器内部に負担がかかり故障することがあります。まずは安全のために、給湯器の電源をオフにしてください。
配管を温める
凍結している部分が配管であれば、タオルを巻きつけ、その上からぬるま湯をかけてゆっくりと解凍します。ただし、熱湯をかけると配管が破裂する危険があるため、必ずぬるま湯を使用しましょう。また、ヘアドライヤーでゆっくり温める方法も有効です。
自然解凍を待つ
凍結が軽度の場合、気温が上昇すれば自然に解けることもあります。給湯器や配管が破損するリスクを避けるため、無理に解凍しようとせず、気温の上昇を待つのも一つの方法です。
給湯器の配管カバーを確認
凍結が発生した原因が、配管の保護不足によるものであれば、今後の対策として保温材を追加で巻きつけるか、配管カバーを強化することを検討してください。
専門業者に依頼すべきタイミング
応急処置を行っても給湯器が正常に作動しない場合や、凍結によって配管が破裂している可能性がある場合は、すぐに専門業者に依頼することが必要です。無理に自分で修理しようとすると、かえって給湯器や配管を傷め、修理費用が高額になる可能性もあります。
以下のような場合には、速やかに専門業者へ連絡しましょう。
- 配管が破裂している: 凍結によって配管に亀裂や破損が見られる場合、配管の交換が必要です。これは専門業者に依頼する必要があります。
- エラーメッセージが消えない: 給湯器にエラーメッセージが表示されたままで、電源のリセットや凍結解除ができない場合、内部部品が損傷している可能性があります。
- 凍結が深刻で解凍できない: 自分で行った解凍作業でも全く効果がない場合は、凍結が給湯器内部まで達している可能性があるため、プロの技術が必要です。
専門業者に依頼することで、凍結によるトラブルが早急に解決し、安心して給湯器を使用できるようになります。凍結対策が不十分で困ったときは、プロの力を借りることが最善の解決策です。
給湯器の凍結を未然に防ぐためのメンテナンス方法
給湯器の凍結は、故障やトラブルの原因となり、突然の修理や交換が必要になることもあります。しかし、定期的なメンテナンスを行うことで、凍結によるリスクを大幅に減らすことが可能です。ここでは、凍結を防ぐためのメンテナンスの重要性と、給湯器の交換時期を見極めるポイントについて解説します。
定期的な点検の重要性
給湯器が正常に機能しているかどうかは、日常的には気付きにくいものです。特に寒い季節に入る前に、定期的な点検を行うことが、凍結やその他のトラブルを防ぐ鍵となります。定期的な点検には次のような重要なメリットがあります。
凍結防止機能のチェック
最新型の給湯器には自動凍結防止機能が搭載されていますが、長年使用しているとこの機能が劣化したり、正しく作動しなくなることがあります。点検時に、凍結防止機能が正しく働いているか確認し、必要に応じて修理やメンテナンスを行うことが大切です。
配管や部品の状態確認
給湯器本体や配管に亀裂や劣化がないかをチェックすることも重要です。特に、配管部分が外部に露出している場合、気温の変化によってひび割れや劣化が進行しやすくなります。事前に点検しておくことで、凍結による破裂や水漏れを未然に防ぐことができます。
燃焼効率の向上
定期的な点検により、燃焼効率を最適な状態に保つことができ、給湯器の寿命が延びるだけでなく、日々のランニングコストも抑えることができます。点検を怠ると、無駄なエネルギー消費や不完全燃焼のリスクが高まります。
給湯器の点検は、1年に1回程度を目安に行うのが理想です。特に寒い季節が始まる前に専門業者に依頼することで、冬のトラブルを未然に防ぐことができます。
給湯器の交換時期の見極め
どれだけメンテナンスを行っても、給湯器には寿命があります。一般的に給湯器の寿命は10〜15年とされていますが、使用環境やメンテナンス状況によってはそれよりも早く交換が必要になることもあります。交換時期を見極めるためには、以下のポイントに注目しましょう。
頻繁に修理が必要になる
給湯器が頻繁に故障し、その都度修理が必要になる場合は、交換を検討するタイミングです。特に、凍結や部品の劣化が原因で毎年のようにトラブルが発生する場合、修理費用がかさむことが多く、長期的に見ると交換のほうが経済的であることが多いです。
お湯の出が悪くなる
給湯器の性能が低下してくると、お湯が出るまでに時間がかかったり、温度が安定しなくなることがあります。これは内部の劣化が進行しているサインであり、特に凍結などによる内部損傷が重なると、給湯器自体の交換が必要になるケースが増えてきます。
最新機種の凍結防止機能に注目する
古い給湯器を使っている場合、最新の機種に交換することで、より効果的な凍結防止機能が得られます。最近の給湯器は、より省エネ性能が高く、凍結防止機能も強化されているため、古い給湯器に比べて凍結リスクが低く、長期間快適に使用できます。
寿命に達している場合
一般的に、給湯器が10年以上使用されている場合、いつ交換が必要になってもおかしくありません。特に冬の寒い時期に故障すると、修理や交換までの間お湯が使えないという不便な状況が続くため、寿命に近づいた給湯器は、余裕をもって交換を検討することが大切です。
定期的な点検と、給湯器の状態を確認することで、トラブルを防ぎ、長く安全に使用することが可能です。特に凍結対策は、冬の寒さが厳しくなる前に準備しておくことで、安心して給湯器を使い続けることができます。
まとめ
給湯器の水抜きは、凍結による故障を防ぐために重要な対策です。特に寒冷地や冬季において、定期的な水抜きや保温対策を行うことで、給湯器のトラブルを未然に防ぐことができます。万が一凍結してしまった場合も、応急処置や専門業者への相談で迅速に対応可能です。凍結防止策をしっかりと実践し、冬場でも安心して給湯器を使えるよう準備しておくことが大切です。